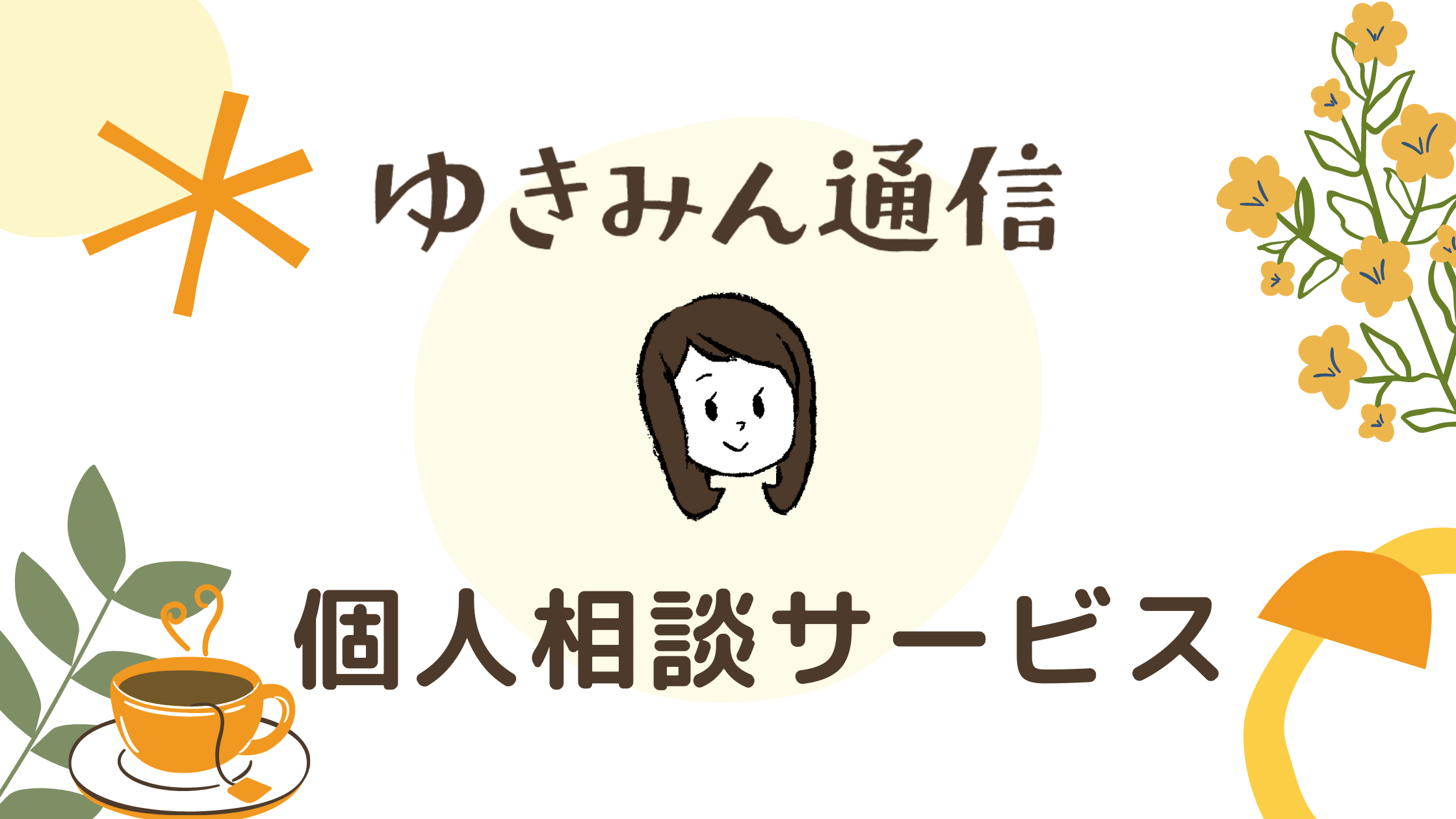生涯のうちで、生涯というのが死を含めるものだと仮定して、私が唯一見てみたいのは、自然の絶景、例えばオーロラとか塩湖みたいなそういう、そういうんじゃなくて、私が死んだ後にみんながどんな表情をするのか、受け止め方、かわし方、私はすごくそれが見たいのだと思う。果たして見ることは叶わないけれど。あの人は泣くのだろうか、何事もなかったように振る舞うのだろうか、もしくは創作に昇華させたりもするのだろうか。そしてそれらは誰のために。
昔、セキセイインコを飼っていた。
鳥カゴのつり紐は随分古くなっていたのに、誰もそれに気付かなかった。
ある日帰宅したら、鳥カゴは玄関先の石のタイルの上でバラバラになっていて、その中にいた小さな青い鳥はいなくなっていた。
彼女は、間違いなく死んだ。どこかで。でも私はほとんど悲しくなかった。悲しかったのは、飛んでいった、だからもう会えない、と理解したその瞬間だけだった。私は安心した。彼女はもう、私の手の中で死ぬことはない。春の風を、羽の細かなところでたっぷりと感じ、その後に死んでゆく。たとえどこかで猫に食われるとしても。だからこれは、彼女にとっていい終わり方、いい死に方ではないか、と納得してみた。いい死に方。いい死に方ってなんだろう?
小鳥の、そのわずかな重さは、魂の重さそのものではないだろうか。
祖父は私が小学2年生の時に亡くなった。祖母はひどく落ち込み、母は毎日がお誕生日会のように、食卓をごちそうでいっぱいにした。それは祖母のためなのか、それとも母自身のためなのか分からなかったけれど、あるいは二人共のためだったかもしれないけど、それが数年続いたものだから、死に向き合うとは相当なエネルギーを使うんだなと中学生の私は思った。とても他人事のように。永遠に続くお誕生日会。私は毎晩言いようのない不安と後ろめたさを抱えながら夕食の席につき、用意されたものを黙々と食べた。祖父は私が物心ついた頃にはもう寝たきりで、口から食事をとることができず、話すこともできなかった。笑顔は写真でしか見たことがなく、声も思い出せない。父方の祖父も私が生まれるより随分前に亡くなったから、それで私には「祖父」という存在、「おじいちゃん」と呼んでいい存在についての感覚がない。ただ、街で誰かの「おじいちゃん」を目にする時、彼らの歩き方、髪の色、服装、声、話し方、笑い方、どこを取っても私の祖父とはまったく似ていない、本当に、全然似ていないということだけ、私にははっきりと分かるのだった。